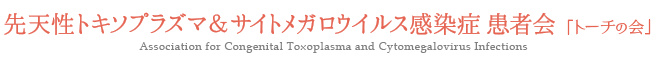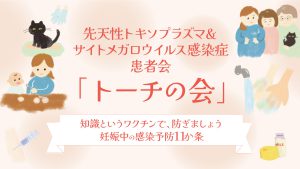おなかの赤ちゃんがトキソプラズマに感染しているかどうか調べるために、出生後にどのような検査を行いますか?もし感染していたらどのような治療を行いますか?


以下の項目のうち、どれか一個でも当てはまれば「おなかの中で感染(先天性感染)した」と診断します。
① 赤ちゃんの血中の抗トキソプラズマ抗体(IgG)が母親の抗体価と比べて高値で持続する、または上昇する時
母親の抗トキソプラズマ抗体(IgG)は胎盤を通って赤ちゃんにもたらされるので、感染していない赤ちゃんでも抗トキソプラズマ抗体(IgG)は陽性です。でも、おなかの中で感染した赤ちゃんであれば、自分でも抗トキソプラズマ抗体(IgG)を作っているので、母親の抗体価と比べて高い抗体価を持続するか、さらに上昇していきます。
② 赤ちゃんの血中の抗トキソプラズマ抗体(IgM)が陽性の時
おなかの中で感染したばかりの赤ちゃんであれば、「最近感染した」ことを示すIgM抗体を産生中です。IgM抗体は胎盤を通過しないので、赤ちゃんの血液中の抗トキソプラズマIgM抗体は間違いなく赤ちゃんが産生しています。ただし、先天性感染していてもIgM抗体陽性が確認できるのは4人に1人くらいですので、陰性であっても先天性感染を否定することができません。
③ 赤ちゃんの血液、尿、または髄液からトキソプラズマDNAがPCR検査で検出される時
人に感染したトキソプラズマはいずれ脳や筋肉などの中に入って動かなくなりますが、おなかの中で感染したばかりの赤ちゃんの場合は、まだ移動中のトキソプラズマのDNAを血液や髄液や尿から検出できる場合があります。ただしこの検査は保険適用外で、実施できる医療機関は限られています。また、偽陰性(感染しているのに陰性になる)も偽陽性(感染していないのに陽性になる)の結果が出る場合もあります。髄液の採取は赤ちゃんに少し負担をかけるので、必ずしも調べないことがあります。この他に胎盤や臍帯血や羊水を調べることもあります。
④ 母親が妊娠中に初感染したことがわかっている場合で、赤ちゃんが抗トキソプラズマ抗体(IgG)を持っていて、かつ何かしらの症状が出ている時
妊娠中に初感染した母親から生まれた赤ちゃんに、先天性トキソプラズマ症として矛盾のない症状が認められた場合には、赤ちゃんの感染の確率は非常に高いと考えられます。通常の診察だけではわからない重要な症状を見つけるために、脳画像検査(脳エコー検査は必須、できれば脳MRI検査まで)や眼科診察(特に眼底検査)を実施します。
ただし、これらの検査を行っても、赤ちゃんの感染の有無が確定できないこともあります。
赤ちゃんから検出された抗体が母親から移行したものだけであった場合は、通常であれば生後6〜12か月で消えるため、定期的に赤ちゃんの抗体検査を行います。抗体が消えるのが確認されたら、感染は否定できます。
一方、一歳になった時に、抗トキソプラズマ抗体がまだ検出される場合は「先天性感染があった」と診断されます。
<治療>
出生時に症状がなくても、先天性感染が疑われる場合はそれが否定されるまでは定期的に受診し、血液検査、必要に応じて脳や目の検査を行いながらフォローしてもらうことが早期発見・早期治療のために必要です。
出生時に症状がある場合はすぐに投薬治療をはじめますが、出生時に症状がなくても先天感染が確定されている場合は、発症予防のために投薬を行うことが推奨されています。
一般的には、ピリメタミン+スルファジアジン+ロイコボリンによる治療を一年間行います。
しかし、こちらは保険適応がないばかりか、国内では販売承認もされていないため、熱帯病治療薬研究班への研究協力として薬剤の提供を受け、治療をおこないます。ただし、研究班に所属している施設はごく僅かで、そうでない場合は個人輸入で取り寄せる必要が出てきます。
また、赤ちゃんの状態によってはこの薬が使えないこともあります。
例えば、新生児期(早産児の場合はもっと長い期間)には核黄疸のリスクがあるので、スルファジアジンは使いにくいです。その場合は他の薬を使うことになりますが、ピリメタミン+スルファジアジン+ロイコボリンほど効果が望めない場合もあります。
おなかの中の赤ちゃんが感染したかどうか調べる方法はありますか?≫
監修:長崎大学 森内浩幸
妊娠中の感染予防のための注意事項-11か条
11か条をかわいいイラスト付きでプリントサイズにまとめました。 トキソプラズマやサイトメガロウイルスの予防だけでなく、妊娠中の様々な感染症からの予防について書かれています。妊娠中の方も、周りに妊婦さんがいる方も、知っていただきたい内容です。